疲れました
まだ余裕の表情の柳さん
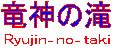

| 金山城は、廃城後400年以上経過し、当時の建物は残っていませんが、戦国時代の城の中心的な防御施設である土塁や堀切の遺構が明瞭に残っており、金山々頂から四方に広がる尾根を造成し、曲輪(くるわ)とし、城が築かれていることがわかります。このようなことから、金山城はその歴史的価値の高さと遺構の残りの良さが評価され、昭和9年(1934)に金山々頂を中心とする尾根部分18.3haが国の史跡に指定されました。 「太田市教育委員会HPより引用」 |
| 戦国時代の城は戦乱の世を反映し、常に生か死かを意識した実戦的な城で、城は「砦」という言葉がイメージするような質素なもので、土塁(どるい)や堀切(ほりきり)などで厳重に守られ、いざとなったら侍だけでなく、領民を取り込み篭城戦に持ちこたえられるよう万全の準備がなされていました。 |
| 金山には戦国時代に城が築かれていました。城というと、まず松本城や姫路城など天守閣のある城を連想すかも知れませんが、金山城は江戸時代の城と違い、日々戦いに明け暮れた時代の城でした。 |
大手門に通ずる正面土塁(防御壁)平成14年に発掘調査により復元した。
今回のハイキングで最後に訪れた子育て呑龍で知られている呑龍様、境内にどっしりと根をおろした見事な枝ぶりの松。樹齢7〜8百年はゆうに経っていると思われる、金山々頂の大欅といずれ劣らぬ見事な巨木。
金山の山頂にどっしりと根をおろす大欅、その幹の太さもさることながら見事な枝ぶり。
金山城の全盛期には、戦国武将がここで「休息」を取ったのかな?、金山城の歴史を全て知り尽くしているようで風格さえ感じさせる。
樹齢7〜8百年は経っているのではと思われる見事な欅の大木、その下に陣取り記念写真。
山頂は目の前、最後の石段に苦戦するメンバ−、頑張れもうひといき。
梅の花をバックに余裕の表情の柳さんと少々疲れ気味の中沢さん。
第11回
参加者17名
07年2月20日天候曇り、第11回ハイキングを太田のシンボル金山に金山城の歴史を訪ねた、熊野町の社会教育福祉センタ−の駐車場に集合、熊野神社の裏手の登山口から入り「平和の鐘」を通り「親水公園」へ、ここから八王子山々頂を経由し「カラタチ沢」へ、さらに「御城道」を通り山頂を目指した、途中「御城道」で見張り小屋の発掘調査現場に立ち寄り調査員に発掘現場で調査の説明を受ける。
金山は近くにありながら意外に登ったことの無い人が多い(参加メンバ−)、歩き初めて約1時間40分新田神社に到着、運動不足のためだいぶお疲れの人もいたようだ、まずは大欅の前で記念写真。
以下太田市教育委員HPより引用



<お礼>
ハイキング愛好会のホ−ムペ−ジに最後までお付き合い頂き有難う御座いました。